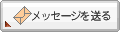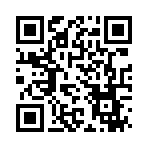2024年04月29日
撮影監督 岡崎 宏三

今回は“従軍カメラマン”の目線で描きました。戦争映画は戦場をいかに再現するかが勝負ですからね。それにスタッフで戦争を知っているのは私だけでしたから。
実は戦中戦後にかけてニュース映画を撮っていた時期があって、そのときの経験から弾をよける姿勢、視点というものを知っている。今回の塹壕からの映像でもあれより高いと撃たれてしまうのです。
それと今回は当時の映像について“1フィート運動”のアメリカのニュースフィルムを活かすということになりましたから、それと今度の映画の画質をどう調和させるのかという点に苦心しました。
不幸中の幸いというべきか、「GAMA」は製作費の問題で企画がスタートしてから1年半程は撮影に入れなかったのですが、その間に使用するニュースフィルムをアメリカから取り寄せて研究することができました。
そこで考えついたのが、アイモという戦争中に使っていた旧いカメラをカムバックさせようということでした。アイモと言うのは、ピントは送れない、ファインダーは正確でないという非常に不便なカメラなんですから当時を再現するには当時の可能な技術で撮るのが一番。
フィルムも今のは映りすぎるので、現像所に頼んでわざと画質を落としてもらいました。「シンドラーのリスト」(1994年アメリカ映画)なんかもこの点では必ずしも成功しているとは思ってなかったのですが、今回はラストの救出シーンの脱色などいい結果になったと思っています。
あと、壕の中は「闇」ですからね。上からの光源を使わないで、ロウソクのあかりですからカットごとに考えました。
要は、人間の力でフィルムを再現しようということだったのです。
この点では、糸満市をはじめ地元の人たちのバックアップ体制も大きな力でした。撮影現場が全部糸満に集まっていて、ガマのセットも製糖工場の倉庫の中に作れたし、協力してくれたゴルフ場の中に本当のガマがあって入り口付近はそこで撮れました。
でも、天候だけはどうにもなりません。沖縄戦は、後半はほとんど雨だったと記憶にはある。例えば、雨の中を子どもを探すところなんか、地元の人が200人も集まってくれたのに、その日は晴。手前に雨だれを使うといったこともありました。
ていねいに作るというのは決してお金をかけることじゃない。人間の能力をフルに発揮してつくれば、世界のフィルムに負けないものになるはずです。
このような考え方、姿勢で撮り、作った映画が、上映(運動)の面でも貫かれ、広がっていくことを期待しますし、それに成功すれば“新しい映画づくり”といえるのではないでしょうか。
プロフィール
映画との関わりは、1936(昭和11)年、新興キネマ大泉撮影所の入所までさかのぼる。撮影した作品は146本を数える
代表作
御用金(1969年)
恍惚の人(1973年)
ザ・ヤクザ(1974年)
ねむの木の詩がきこえる(1978年)
アラスカ物語(1978年)
戦争と青春(1991年)
Posted by バヨリン弾き at 22:35│Comments(0)